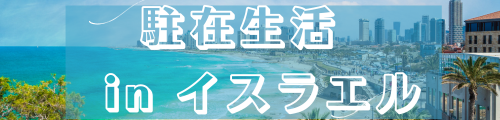【イスラエル駐在★祝1年】ミドルスクール生活、Grade 7も終盤!インターナショナルスクール奮闘記(5)

シャバット・シャローム、a-box-of-chocolateです。
イスラエル駐在生活も無事に一年を迎えました!2024年4月、イランからのミサイル攻撃で始まったわけですが、あれから1年…戦争サイドを見ると、サイコロでいうとゴール直前で「振り出しに戻る」のマス目に止まった気分です。
停戦とは?という疑問がつきまとう数か月でしたが、国外の人には想像もつかないほど、「普通」の暮らしができるテルアビブ。一年中天気がいいし、寒くないし、海はきれいだし、なんやかんやで駐在生活はとても楽しいです。
そして!前回の投稿から数日後、私のブログがグーグルアドセンス承認されました!その瞬間、サイトのあちこちが広告だらけに…。こちらも手探り運営なので、少しずつ改良していきたいと思います。
さて今回は久しぶりに「インターナショナルスクール」のことについて書いていきます。クオーター3(三学期)も終わって、いよいよ最終学期に突入した子どものミドルスクール生活。1年目の学校生活についてまとめてみたいと思います。
目次
”アメリカ式インターナショナルスクールは「緩い」説”は本当だった!?イスラエルでの中学校生活1年目を振り返る!
6月中旬で、今年度が終了するインターナショナルスクール。現在は最終クオーター(4期目)に突入しました。4月上旬は「パスオーバー」というイスラエルの祝日やイースターホリデーのため、2週間ほどの春休みがあります。
つまり、今年度は残り実質二ヶ月しかありません!学費がべらぼうに高いので(単純計算、一日三万円くらい⁉)なるべく多く学校に行ってほしい!と願ってしまう親の欲目に逆らうがごとく、とにかく登校日数が非常に少ない学校生活です。
宿題がない!と言い張る。授業では実際、何を学んでいるのか?
一言でいうと、中学生とは思えないほど勉強量が少ないわが子。すみません、サンプル数1なので全く参考にならない話ですが、自宅で勉強している気配がほぼなく、それでもなんとかなってしまっている学校生活=アメリカンスクール。
語学力の面ですが、日常生活での友達同士での会話はスムーズにこなせるようになったようです。しかし…授業中に配られているプリントも、提示されている課題も、相変わらず語彙力高くて本当に一人でこなせているのか?と疑いたくなるレベル。
ちなみに、以前は細かくチェックしていた各授業の進捗状況も、子どもがクロームブックを見せてくれなくなったので本人任せにしています。中学生にとって、学校での出来事や授業のノートや提出物を親に見られるのは恥ずかしい。その気持ちはすごくわかるので。
散らかっているプリント類だけは、片付けがてら見ていますが…
もはや私も調べながらでないとフォローできないほど、数学や生物は専門用語だらけで全く意味が分かりません。小テストや単元テストの結果は、うーん、これで大丈夫なの?というレベルではあるのですが、「英語の理解力が追いついていない」という言い訳は、いつまで切り札として使えるのかな?というほど甘めの判定にも感じます。
子どもの性格なのでしょう、完璧に覚えていなくても大丈夫!と楽観的にとらえているのか、その時さえ乗り越えればそれで終わり、という感じで、のら~りくら~りと学校生活を送っているのです…。
家でももっとやってほしい、と思い、せめて図書館で借りてきている本をしっかり読み進めなさい、とは声を掛けますが「期限はまだ先」とか「学校で一日中英語やってるから大丈夫」とか、非常にあっけらかんとした様子で、日本語のユーチューブ動画を楽しむ放課後ライフ…。
私の想像の斜め上を行くほど、「ゆるい中学生」になってしまいました。
そんなミドルスクール7年生の「学習内容」ついてご紹介します。
★Humanity (人文科学、歴史、語学)
ネルソンマンデラの「アパルトヘイト政策」などについて調べ学習をしていたときのプリント。かなりの量のリーディング、そのあとにグループ学習で「コミュニスト」の立場で感想や意見を書いています。
ブックスタディのようなsessionも時折やっています。自分の主張→サポート→理由、を論理的に書いて表現する練習のようです。英文はだいぶ幼い感じですが、何かしら書いて表現する力も、少しずつ身についてきました。
何かの単元が終わった時のまとめ?感想文?の用紙。とにかくプリント整頓をせずに放置しまくる子なので、私が勝手に拾って読みました…。
EAL(English as Additional Language)クラスにいるのによく頑張ったね、you should be proudとの先生からのフィードバック。とにかく褒めちぎってくれるのです。
★数学
Algebra (代数学)を主に学んでいます。比例、反比例、一次関数など。この辺の単元は、日本の中学生が習うことと大差ないと思うのですが…問題は専門用語。variables(変数)、The greatest common factor(最大公約数)など、日本語ではすぐにわかっても、英語で聞かれると「??」となる点も。最初は小学生時代の貯金で簡単にこなせていた数学も、だんだん内容が追いつかれ追い越され、英語で理解しなければいけない範囲に…。
★理科(生物)
先月末に、Science Fairという展示イベントがありました。日本でいう、夏休みの自由研究みたいなものを、授業が一緒のクラスメートとチームを組んで発表会を行う、というもの。
研究テーマ、実験、まとめ、資料の用意、パネル展示制作など、各チームで協力して行い、発表当日は審査員もいる「コンペ型研究発表会」となっていました!
開催場所は体育館。
わが子のチームは、「微細藻類がより多くの酸素を発生するためには?」というトピックでした。microalgaeという単語、初耳です…。イスラエル人の子がいろいろ説明してくれたけど、いまいち理解できなかった私。中学レベルの理科も、英語だとなかなか理解できないし(グーグルレンズ使いましたw)、子どもに適切な質問をして、もっと意見を引き出してあげることもできない大人です…。
ちなみに同時刻にG3~5の小学生の発表・展示もありました。クロームブックでスライドショーを流して自分たちの研究をプレゼンしていた4、5年生。ブースに立ち寄ってくれる保護者や先生に、自分たちの研究内容やポイントを説明する力は、小学生のうちから少しずつ養われているようです。
★音楽 / band
音楽の授業は年間を通じて「バンド(ブラスバンド)」。サイエンスフェアーと同じ日に、バンド&合唱コンサートがありました!Performing Artsなので、発表会に出席すること=ゴール、みたいなものです。
あれだけ嫌がっていたブラスバンドですが、いつの間にか楽器(クラリネット)の演奏も上達して、まさかの最前列に座っていました!写真はプライバシー保護のため割愛しますが、中学校の吹奏楽部の定期演奏会そのものです。でも、部活ではなくて”授業”というところが大いなる違いです。
★宿題、小テスト、レポート、テスト…すべて点数化される成績評価
上記の科目の他に、美術、体育、EAL(英語の補習クラス)、ホームルーム活動があります。
成績については、考え方次第です。英語ネイティブ、またはEALにいる必要のないレベルの生徒は、ストレートA+を取って当然!という保護者&子どももいれば、アートや音楽を楽しみたい子、スポーツやりたい子など、様々。それは日本の中学生も同じかと思います。
ちなみに放課後アクティビティは、今期は念願の高校テニスチームに加入させてもらえたので、週三回練習に参加しています。
日本の公立小学校からインターナショナルスクール入学で、どうなることやら?と思いましたが…想像以上の適応能力の高さを発揮しているわが子。
学校のことをほとんど話してくれないタイプなのですが、親には踏み入れられたくない交友関係や、ほっといてほしい学業関連のこともある年頃だと思いますので、このまま無事に年度を終えられれば、それでいいかな?と思っています。
学校を休みにして行われた「三者面談」
サイエンスフェアーやコンサートとは別に、学期末面談もありました。
今回はStudent-led Conferenceということで、生徒が自分でデジタルポートフォリオを作り、今年度の振り返りシートを見ながら親にプレゼンする、という30分の面談時間が組まれていました。
木曜日の午後、そして金曜日を終日休校にして行われた面談。先生が残業して放課後やる、なんて意識は皆無です(笑)。
そしていざ行ってみると…
冒頭の校長の話で、プレゼンは英語でも母国語でもどっちでもいいです、というアドバイスが!そしてもちろん、日本語を選択したわが子。ポートフォリオは、学校側が用意したテンプレに沿ってちゃんと英語で作ってありましたが、「これ読んで。」と丸投げ。
親子でそれぞれ質問し合ってみよう!というプリント(英語)もほぼ無視。30分間、ひたすらに日本語でしょうもない話をして…なんとも不毛な時間でした(笑)。
ポートフォリオには、生物とヒューマニティが難しくて戸惑うことも多かったけれど、先生やクラスメートに助けてもらいながら乗り切った、「いい話」が書いてありました。こうした「先生ウケのよい作品」を作るのが得意な子なので、私は半信半疑のまま面談は終了。
このプレゼン、親子4組が1クラスに集まって同時に個別発表をするという予想外の展開で、ホームルームの先生ともあまり話せず。もらったフィードバックは”I’m proud of you”、ひたすら褒め言葉をくれるのはありがたいけど、そうじゃないんだわ!!という気持ちになった私は、典型的なアジア人でしょうか…。
プレゼンのあとは、「ソーシャル・タイム」。カフェテリア前で飲み物やお菓子が配られ、保護者同士または先生と自由に話してください!と野に放たれました。
そこで、EALの先生とだけ話すことができたのですが、「補講クラスでのんびりと自分のペースで頑張っている」と褒め言葉をもらって終了。「日本語の維持にも興味をもてていなくて…」という相談もしてみましたが、母国語の本やドラマで覚えたら?と言われて終わりました。
アメリカンスクールには、子どもにダメ出ししてはいけない、という戒律でもあるのか??というほど、子どもを褒めて、一貫してgrowth-mindsetを伸ばすことに徹しているように感じます。
growth-mindsetに沿った発想は「今はできていないことも、まだできていないだけで、これから出来るから大丈夫!」というふうに物事をとらえます。出来ていないことにフォーカスするのではなく、できるようになったこと、これから頑張れば出来るようになることを伸ばしていこう、という声掛けをする教育なのです。
この辺は、文化的な大きな違いだと思います。日本の教育では基礎固めに徹してから大きなステップに踏み出す、細部をかなり丁寧にやる、という教育方法が大部分を占めますが(たとえば、漢字の”とめ・はね・はらい”など)、アメリカンスクールでは、まずは大きな枠組みを捉えることから始めて、必要に応じて徐々に細分化して学ぶ、というマクロな視点を持って取り組んでいるように感じます。
大概のことはオールオッケーさ!というノリに感じなくもないのですが(笑)、郷に入っては郷に従え、既存の枠組みになんてとらわれず、のびのびと学校生活を楽しむという点においてはベストアンサー!と私も感じています。
日本語は?という恐ろしい現実から、親子で逃避行中!
さて英語力に関しては、子ども本人の「困り感」がないのであれば、もはや私があれこれ言っても仕方ありません!しかし!日本の新年度を迎えて思うのは、【日本語での義務教育をどうするのか】…(涙)
放棄するつもりはないのですが、日本から持ってきた検定教科書、折り目すらない美品状態で中1が終わりました。そして先日大使館から中2の教科書が配布されて、、、「学年が上がった」という現実を突きつけられました。
せめて、国語と道徳の教科書を「日本の語の読書教材」として読んで!漢字読めなくなるから!としつこく言っていますが、母国語なのに全くやる気がない。漢字が読めなくて困ったらどうしよう?とか、想像すらしないのか…?「Chat GPTに聞けば大丈夫」とか言って交わされます…。
それもそのはず、現在、アメリカンスクールには同級生の日本人が一人もいないので、モチベーション維持できないのは想像できます。補習校もない。そして、数学や生物を含めて「英語」で覚えた専門用語を、日本語でも完璧に理解するところを目指すとしたら、相当な努力が求められますが、その「必要性」がないのです…。
改めて思います、海外駐在で「バイリンガル教育」に成功しているご家庭は本当にすごいです。
家庭では親子での会話、主にユーチューブ動画からの口語表現しか日本語に触れていないわが子、数年単位でこんな生活していたらどうなっちゃうのだろうか?と不安要素満載です。一方、学校では日本語をしゃべることが一切ない(話す相手がいない)ので、そこはメリットとしてとらえたいと思います。
我が家の教育は「反面教師」情報でしかありませんが、このご時世、海外受講できる日本の教育プログラムや通信教育(Z会など)もたくさんあります!
【考察】「母国語維持」と「英語力」、どちらを優先するべきなのか??
本題から少し外れますが、いわゆる「帰国子女」であるわが子の語学習得の過程から感じた、私の見解を記します。
家族での海外駐在は二回目で、前回(ヨーロッパ某国)では日本人学校に在籍していたわが子。当時は小学校入学のタイミングで、現地校を選べばその国の言葉をすぐに獲得できた可能性も非常に高いです。
しかし、あえて日本人学校に入学して【日本語】でみっちり学ばせたことは間違っていなかったと思います。その後、小4~小6は公立小学校にいましたが、帰国後の学校生活にはスムーズに適応できました。
むしろ日本人学校の方が教育レベルがかなり高く、小学校低学年という学校生活の基礎を整えるときに先生からたっぷり目をかけてもらえたことで、外国にいながらも漢字や計算など日本語で学ぶことに集中できていました。
ほぼ日本語で暮らしていたとはいえ、英語に触れる機会もそれなりにありました。当時はヨーロッパのサッカーリーグ情報やテニス選手のプレー動画など、ユーチューブやテレビで全て英語で視聴していました。そして学校で英語の授業もあって、フォニックスやアルファベットの書き方などは低学年のうちにマスターしています。
帰国後から今日まで、今度はメジャーリーグ(野球)にハマり、MLBのゲームや動画を英語で視聴。小さい時から英語の動画を英語で見ることに違和感がないのか、訳そうとしたり調べたりしている素振りもありません。
英語はあくまで好きなこと(スポーツ)を知るためのツールでしかなかったわけですが、日本人としてのアイデンティティもきちんと養われていますし、なによりこの素地(主にリスニング)があったおかげか、かなり早い段階でアメリカンスクール(英語オンリー)の環境に適応し始めていったのかな、と感じています。
今後、イスラエル駐在がいつまで続くかわからないのですが、「日本人として、日本語での思考力が育った」ところまで日本の教育を受けさせることができてよかったなと感じています。マルチリンガルな子が周りにも多い今の学校で、英語はあくまで「みんなで理解しあうための共通言語」なだけです。私自身の生活や交友関係もそうです。
あくまで持論ですが、海外に出てみると想像以上の「日本崇拝」に近い褒め言葉をもらうので、やはり「日本人であること」をしっかり確立するためにも、「母国語としての日本語」を幼少期からしっかり身につけることはとても大切だと思います。そのうえで、日本の文化や良いところを海外の人に説明できるだけの「英語力」をプラスアルファで身につけることができたら、子どもの人生がもっと豊かになるだろうなと感じています。