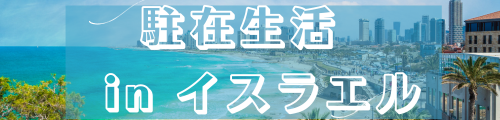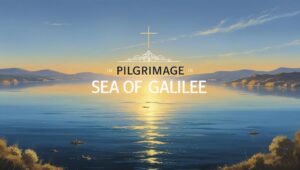【イスラエル駐在】インターナショナルスクール生活、1年目が終了。学力の指標を表す「MAPテスト」から読み解く子どもの成長!
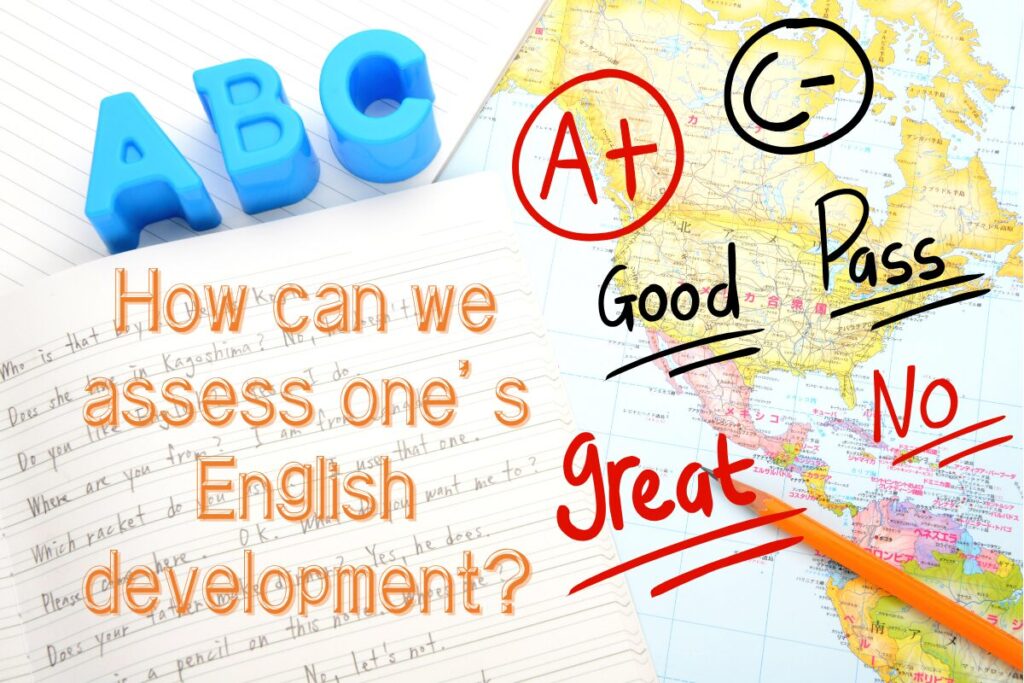
2025年もあっという間に半分が終わり、7月になりました!真夏のテルアビブより、a-box-of-chocolateです。怒涛のイラン戦争が終わったと思ったら、あっという間に夏のリゾート気分が漂い始めたイスラエル…!この切り替えの早さをもって、イスラエル人はせっかちだ、と形容するのにふさわしいのかな…などとのんびりと反芻している私です。
さて、戦争のせいで思いがけない形で強制終了させられた、子どもの学校生活。6月12日(急襲前日)を最後にぷっつりと学校が終わってしまい、強制的に夏休みがスタートして半月以上が経過しています。
インターナショナルスクール関係の友人・知人でイスラエルに残っている人は、ほぼ皆無!!!みーんなとっくに自国へと退避・帰国・または海外バカンスへと出かけています。戦争があってもなくても、夏休み=自国(またはリゾート地)で過ごす、みたいな空気が一般的なのですが。なんでみんなそんなにお金持ちなの??そんなに仕事休めるの??というのがまず第一の感想です…。社畜根性丸出しの日本人家庭とは別世界ですね。
そんなわけで、特に何もせずダラダラしている、最高なのか最低なのか分からない夏休み。日本語の動画漬けになっている我が子ですが、一体学校ではちゃんと成果が出たのか?そのヒントは、「MAPテスト」の結果にありました。
※これまでのインターナショナルスクール生活全般に関する記事はこちら↓
目次
英語版「全国学力テスト」。MAPテストでわかる「到達度」とは?
MAP Growth Testとも呼ばれる学力テストは、Measures of Academic Progressの略称です。直訳すると「学業成績評価尺度」。学校内で習ったことに基づく定期テストや単元テストではなく、いわゆる「外部共通テスト」。「NWEA(Northwest Evaluation Association)」という教育機関が提供するコンピューターベースのテストです。
☆このテストの特徴
①computer aduptive(アダプティブ方式)
受験者の回答結果に基づいて、次の問題の難易度が自動的に調整される形式です。正答すればより難しい問題が、誤答すればより簡単な問題が出題されます。
②時間制限なし
だいたい30分から1時間程度で終わるようですが、どれだけ時間をかけてもよいテスト。難問連発(=優秀な子)は時間がかかるでしょうし、どんどん簡単になっていって、さっさと終わる子もいるので人それぞれです。
③実施回数:年2回
一回目は、学期が始まってすぐの9月頃(秋)に受験し、二回目は4月~5月頃(春)に受験。二回の受験結果を比較して、伸び率を確認します。
④科目:学校・学年によって2-4科目。ミドルスクールは4科目でした。
Math(算数)
Reading(読解)
Language Usage(文法)
Science(理科)
「テスト結果」からわかること。
まず、MAPテストで測れる領域は以下の通りです。
- 読解:文章理解し、推論能力を測定。様々な形式の文章を理解し、意味を解釈する力を示唆。
- 文法:文法、文構造、全体的な言語使用能力を測定。ライティングとコミュニケーション能力を評価する上で重要。
- 数学:問題解決能力、数感覚、数学の概念に関する知識を評価。簡単な算数からより高度な代数レベルの推論まで、生徒のレベルに合わせた問題が含まれる。
- 理科:生命科学、地球・宇宙科学、物理科学の3つの主要領域を網羅。STEM教育の取り組みを支援する上での指導方法考案に役立つ。
次に、テスト結果をどのように取り扱うのか、という「目的」も明確にあります。
- 熟達度の評価:同じ学年の他の生徒と比較して、自分の学業成績がどの程度であるかを正確に特定。
- 進捗状況の追跡:テストは1学年で複数回実施されるため、学校は、生徒が1回のテストから次のテストまでにどれだけ進歩したかを正確に把握できる。
- カリキュラムの調整:教師は生徒のニーズに合わせた授業計画を作成できる。
- 学業支援の提供:学習障害など、なんらかのリスクを抱える生徒を早期に特定することで、早期に適切な介入が可能になる。
- 国家基準との比較: MAPテストは国家基準および国際基準に準拠しているため、個人の学業成績の明確な水準がわかる。
私が思うに、「アダプティブ方式」というところがポイント。優秀な生徒をAdvanced course(先取り学習コース)に入れるのが普通であるアメリカの教育システムにおいて、授業で教わったこと以上に理解力がある子にはどんどん先取りさせることができます。そうした「優秀な生徒」に対する支援も充実させることができる点が、日本の「全国学力テスト」との決定的な違いだと感じます。言い換えると、全体の底上げというよりは、上を伸ばしていくための指標でもあるのかなと。
特にインターナショナルスクールでは、学年相当の内容=自国のカリキュラムで学習済み、というパターンも多々あります。既習済みの内容を二回やるより、先へと進んだほうが将来も安泰、という考えの保護者もいるので、そういうニーズにも答えられそうです。
実際、どのくらいのスコアが取れるのか?どうやってスコアを見るのか?
このテストは、学校からも「事前対策は必要ありません」と通達されていたとおり、「ただ受けるだけ」のテストでした。結果も忘れた頃にやってきた…という感じなのですが、最新のスコアを見ると、秋(2024年9月)に受験した分との「比較」が示されていました。
ちなみに、テスト結果はPDFファイルになっているものが、Power Schoolという学習ポータルサイトを通じて配布されました。
上記は、スコアのサンプルページなのですが・・・正直、非常に見づらい&わかりづらい!
英語のページ、そして日本語で書かれた「MAPテスト」に関するページもいろいろ読み漁りましたが、わかったようなわからないような…。
以下、チェックポイントを挙げます。
①青の棒グラフ→受験者のスコア指標
②濃いオレンジの棒グラフ→同じ学校の受験者の指標
③黄色の棒グラフ→全国平均の指標
④Goals Performance(パフォーマンス五段階評価)
Low(21%以下), LoAvg (21%~40%), Avg (41%~60%), HiAvg (61%~80%), and High (80%以上).
⑤Lexile® Range
具体的に見ていきます。
まずは数学。
え…うちの子天才か…?
日本でごく普通の公立小に通い、むしろ算数苦手とすら言っていたのに、めちゃくちゃ上位です。Percentile Rangeの意味がわかりづらいのですが、太字になっている94という数字を例にとります。それは、全体の94%は自分より低いスコアで、すなわち自分より上の点数を取った人は6%、ということを示しています。パフォーマンス5段階評価もHighを得ています。
「FA24」は2024年秋受験の結果、「SP25」は2025年春受験の結果です。数値もしっかり伸びているのがわかります。
そして右端の青い水玉の棒グラフは、「次回のテストで期待される数値」だそうです。いつまで維持できるかわかりませんが、アジア人の数学無双説は本当だったようです。
かたや、リーディング。
本当にこれで学校生活だいじょうぶかぁ~~~???!という、衝撃の点数…。底辺5%の読解力、という現実です。。。でも、これは本当に仕方ないのです。以前の記事でも書きましたが、Grade 7レベルの課題プリントや授業中の読み物は、筆者の体感で英検準1級レベルです。ただの日本人中学生が突然全部理解できるはずもありません。秋のテストと比べても、点数も微増、という点が悲惨さを物語っています(涙)。
そしてこの項目にある、Lexile® Range(レクサイル指数、詳しい内容はこちらのブログが参考になります)について。
【画像出典】
えぇ…このチャートで行くと指数 435L-585L相当の我が子は、小学校2~3年生レベルの英語の本が適正語彙力、ということになります(涙)。
英検での相関でいくと、以下の通りです。
【画像出典】
https://www.eiken.or.jp/association/info/2016/1227_01.html
550L前後のレベルは、英検だと4~3級程度の実力。この指数、かなり適格だと思います。G6-8(ミドルスクール)=1000L~1100L前後の指数は欲しいところだとすると、やはり英検2級~準1級に受かっていないと厳しいレベル、ということになります。

想像してみてください。小学2~3年生に中学2~3年生の国語の教科書を読ませたら、どの程度理解できるでしょうか…?
ちなみに英検1級でも1300L前後ですので、アメリカ現地校だと高校生レベルということですね。上記の英検の調査結果によると、「英字新聞がスラスラ読める語彙力」相当です。
スペースの都合上画像は省略しますが、Language Useはかなり伸びていました。【英語】という言語自体の運用能力は着々と上がっているようです。こちらも割愛しますがScienceはボロボロでした。専門用語が難しすぎるため、こちらは学年相当に追いつける日は来るのだろうか・・と不安です。
一長一短では身につかない【読解力】。やはりカギは「読書量」!
この結果を見て思いましたが、やはり「読書」って大切です。地味に地味に音読を重ねる日本の小学校教育、あれは正解だと思います。言葉を目で追う、発音がわかる、発声できる、そして意味も分かる。このマルチタスクを瞬時にこなすのって、繰り返し繰り返しの鍛錬が必要なんだと思うのです。
ちなみに私自身は帰国子女ではありませんし、スピーキングは大学時代に取り組んだ多読・音読で伸ばしました。
英語に関しては小学校低学年レベルの読解力しかないわが子にも、簡単な英語でいいからどんどん読みなさい、と言ってはいるものの、そう簡単に読書しない世代というか、個性というか。
私の小中学校時代は本の虫だったのに、わが子となると本を読ませることがこんなに大変だとは。あとは、本人が危機感を覚えるまで何もしないだろうなと思っています。もう幼児ではないので、私がどうこうできる問題でもないです。
インターの先生たちも、読書をかなりすすめてきます。図書館で借りて読める環境にはあるので、行動を起こすか起こさないか、どうやって時間を使うか、そういう意識ができる子は伸びていくのでしょうね…。(理想)

一日中英語で過ごす環境にいるせいか、日常会話で必要な「スピーキング能力」の方が先に伸びてきたなと感じます。しかし、「日常会話程度の英語力」と「学習言語としての英語力」は全く別物です。後者(アカデミック英語)が身につくには数年単位の忍耐強い学習が必要です。
【日常会話レベルとは】
“Does it make sense?” “That’s a good question.” “Hey, it’s not fair!” “I’m not supposed to do it”など、学校で日常的に使う言葉を、(おそらく意図的に)家で使うことがあります。
他にも、”your entire life” “behind the scenes” など、「それどこで習ったの?」というフレーズを発していることもあるので、どこかで見聞きして覚えている英語もあるようで、時折びっくりします。