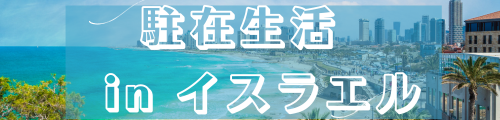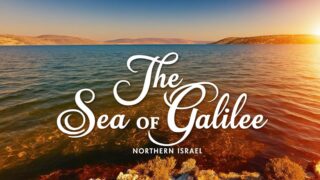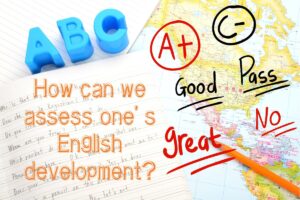【イスラエルで聖地巡礼】イエス・キリストの足跡をたどる旅inティベリア(Tiberias)!ガリラヤ湖畔で街歩き♪
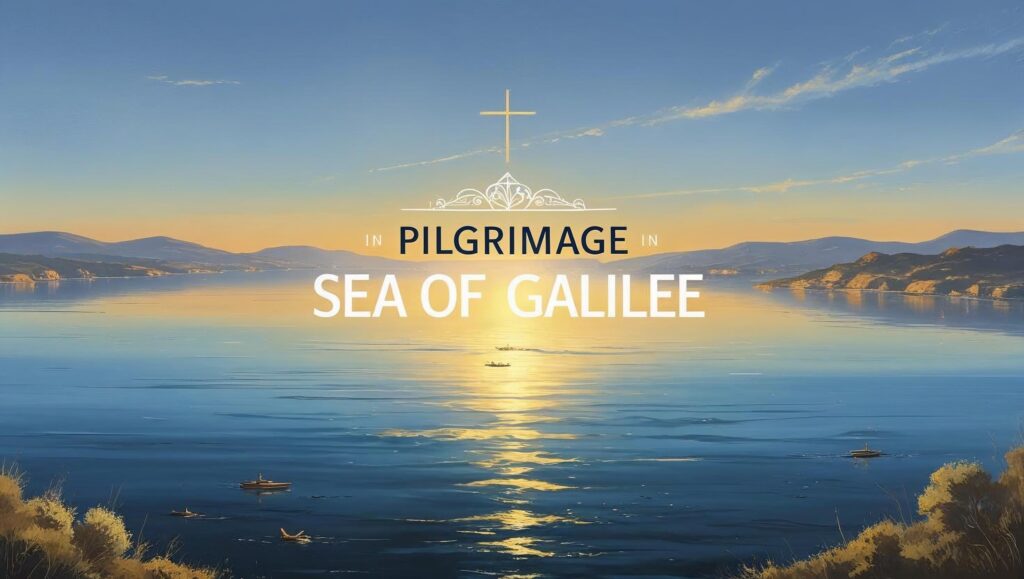
こんにちは、a-box-of-chocolateです。気づけばイランとの戦争から一か月が経ちました。喉元過ぎれば熱さを忘れるとでもいいましょうか、そんなこともあったかな?という雰囲気です。7月のイスラエルはホリデーシーズン、あちこちのビーチの人出は増える一方、賑わいも増す一方です。
テルアビブも暑くて屋外は30℃を超えていますが、昼間でも窓を開ければ心地よい風が入ってきます。
それでも、イスラエル人はエアコン大好き!ショッピングモールやスーパーなど室内施設は凍えるほど寒く、足元から冷えていくほど…。「エアコンの設定温度を28℃にして、地球温暖化対策を!」なんてエコフレンドリーなことを実践している国もあるというのに、そんなのどこ吹く風!です。(笑)
さて今回は「ガリラヤ湖畔での聖地巡礼」がテーマなのですが、これは暑さが本格的になる前、6月上旬に出かけた時のレポートです。イランとの戦争が始まる直前で、あのときはまさか一か月後にこんな風に世界が変わるとは思ってもいませんでした…。
イスラエル北部にあるガリラヤ湖。キリスト教関連の教会や史跡など、見どころ満載です!
目次
キリスト教伝道の舞台、ガリラヤ湖畔(Sea of Galilee)
はじめに。私はクリスチャンではありませんし、キリスト教については「その名前を知っている程度」という浅知恵しか持ち合わせていません。せっかくイスラエルに住んでいるので宗教関連の聖地巡礼もしてみたい、というミーハーな気持ち半分、観光半分で巡ってきましたので、「大人の社会科見学記録」だと思って読んでいただければと思います。
①イエス・キリストとイスラエルの関係
まず大事なポイントとしては、「イエスはユダヤ人であり、(現在の国土区分である)イスラエルで生まれた」ということです。出生の地とされているのは、現在パレスチナ自治区にあるベツレヘム(Bethlehem)。そして、幼少期から成人まで育った場所がナザレ(Nazareth)です。
そして、タブハ(Tabgha)というガリラヤ湖畔の街を中心に、布教活動をしたと言われています。磔にされる直前はエルサレム(旧市街地)を回り、お墓もエルサレムにあります。
どの土地も、「旧約・新約聖書」に描かれている場所らしいので、聖書に照らし合わせて巡る巡礼者もたくさんいます。
②ガリラヤ湖畔(ティベリア地方)での布教活動
Upper Galileeと呼ばれる湖の北側エリアにイエス所縁の土地や教会がありますので、ご紹介していきます。
(1)カペナウム(クファル・ナフム)Capernaum (Kufar Nahum)
ナザレを去ったあとのイエスが住み始めた場所だと言われているのが、カペナウム。
想像していた以上にしっかりとした「遺跡」でした!
平日に訪れたせいか、閑散としていて観光客は皆無に近い状態でした。
「ザクロ」や「スコットのお祭り」で使われる植物のモチーフなどが残された石柱。全部ユダヤ教由来です。
イエスが説教したと言われているシナゴーグ。今まで見たことのあるどのシナゴーグより立派で、まるで神殿でした!
となりにあるのは、「ピーターの家」。ピーターって誰?と思った読者の皆さん。私と同じです。Peterとは、この文脈では「ペテロ」のことです。
以下、ChatGPTにまとめてもらいました。
ペトロ(ペテロとも)は、イエス・キリストの十二使徒の一人で、初期キリスト教の重要な人物です。以下に彼の主な特徴をまとめます。
1. 本名と背景
– 本名はシモン(シメオン)で、イエスによって「ペトロ」(岩を意味するギリシャ語)と名付けられました。
– 職業は漁師で、イエスとの出会いもガリラヤ湖の湖畔でのことです。
2. イエスとの関係:
– イエスの最も親密な弟子の一人であり、多くの場面で重要な役割を果たしました。
– イエスの変容や最後の晩餐など、多くの主要な出来事に立ち会いました。
3. 初期教会の指導者:
– イエスの死後、初期キリスト教会の指導者となりました。
– 使徒ペトロの手紙では、信者たちを励まし、教えを広める努力を続けました。
4. 後の伝承と殉教:
– 伝承によれば、ローマで逆さ十字で殉教したとされています。
– カトリック教会では初代ローマ教皇とされ、「聖ペトロ」として崇敬されています。
ペトロは、聖書の中で重要な役割を果たし、キリスト教においても広く尊敬されている存在です。
というわけで…この「ペテロの家」、現在はきれいな教会が上に立っていて、教徒にとっては非常に重要な場所だそうです。そしてペテロ氏も重要な人物!
遺跡の様子。
教会内部は一部ガラス張りになっているので、ペテロの家(オリジナル)を上から眺めることができます。
太陽光を360度取り込める、明るい教会でした。
屋外にあった「ペテロ像」。元フィッシャーマンなだけあって、なかなかいかつい体格です。足元につった魚がシンボルとして転がっています。
カペナウムの敷地内のほとりからは、美しいガリラヤ湖が望めます。
この湖、イエス・キリストにまつわる様々な伝説があるのですが(海面を歩いたとか、嵐を鎮めたとか)、実際のところ、ここは「海」ではなくて「湖」で、対岸まではっきり見えてしまうほどのサイズ感なのです…。そういった「言い伝え」を信じるだけの「信仰心不足」の私は、「へえ~本当か?」と感じてしまうエピソードなのでした。
しかし、文明が発達した今でこそ「ガリラヤ湖=小さい湖」という認識ですが、イエスが布教活動に励んでいたのは1世紀頃。当時の人々は、まったく別の角度から世界を見ていたのだろうなと思うと、非常に興味深い話です。
(2)ギリシア正教会(12使途教会)
カペナウムのすぐ近くにある、ピンクの屋根がまぶしい「ギリシア正教会」。
カペナウムの敷地内からも見える距離なので、近くまで行ってみたのですが。
インターホンは壊れているし、誰も出てこないし、ドア閉まってるし…入れませんでした(涙)公式HP上は、毎日開いているとの記載があるのですが…残念ながら外から見るにとどまりました。
不自然なほどにピンク!な外見がなんとも言えませんでしたが(塗装し直している説)、ガリラヤ湖を背景に非常に映えていました。
(3)山上の垂訓教会(Church of Mount of Beautidudes)
時間の都合上、今回は車窓から眺めただけだったのですが。
ちょっとした小高い丘の上にあります。
「山上の垂訓教会 90, Tiberias」
https://maps.app.goo.gl/35o2La88CyCJibK37
ここは、1930年代に作られた教会です。Wikipedia によると、「山上の垂訓(さんじょうのすいくん)」とは、新約聖書「マタイによる福音書」5章から7章と、『ルカによる福音書』第6章にある、イエスが山の上で弟子たちと群集に語った教えのことに記されているイエス・キリストの説教で、キリスト教の倫理や教えの基礎となるものです。
(4)ペテロ首位権の教会 Church of the Primacy of Saint Peter
続いて訪れたのがこちら。
ペテロ首位権の教会
イエスがペテロと出会い、一番弟子にしたと言われている場所。
後の「Pope(ローマ教皇)」一覧表もありました。
レンガ調のこじんまりとした教会です。
写真の石壇は、イエスが腰掛けていたとされる場所。
ガリラヤ湖畔にあります。
教会の中にも自由に出入り可能です。
キリスト教の教会も、シナゴークも、モスクも、全て存在する国、イスラエル。
外にはパンと魚で空腹の人々を満たしたという伝説を模した絵や、イエス&ペテロの銅像もあります。
※今回は時間の都合で中まで訪れなかったのですが、「パンの奇跡の教会」もすぐそばにあります。
この湖畔の石にはご利益があると考えられていて、石を拾っている人がたくさんいました。
(5)イーガル・アローン・センター Yigal Allon Centre
https://maps.app.goo.gl/8QHPAS1bNFyyDP1Q6
https://yigal-allon-centre.org.il/en/the-museum/the-ancient-boat
ここには、「イエスの舟」と称される古代の舟(この土地で発掘されたもの)が展示されています。2000年前の木船だそう!
1986年に、干ばつにより干上がったガリラヤ湖の湖底から見つかった代物。発掘調査にも復元にも、膨大な時間をかけた「世紀の大発見」です。
イエスやペトロが実際に乗っていたかどうか、という確証はないものの、時代考察や舟の原材料などを見るに、聖書の内容と一致する時代(紀元1世紀)の舟であろう、とのこと。
浪漫がありますね〜。
地元の子どもが社会科見学に来そうな場所でした。
ガリラヤ湖も空もとても青くて美しく、どことなく神聖な空気が漂っている地域だなと感じました。
この博物館はかなり小さいのですが、屋内施設がほぼないガリラヤ湖周辺の街歩きの中では、涼しい室内で一休みできます。
ミュージアムカフェの店員さんが日本語ペラペラで、まさかの日本語でコーヒーを頼んだり世間話をしたり、という思いがけない体験もしました!
聖書に興味がある人もない人も、ぜひ歩いてみてほしい「ガリラヤ湖畔」!
さて、今回はカペナウム~タブハ村周辺の散策についてお届けしました。キリスト教徒にとって重要な「聖地」を巡ってみて、私も聖書の世界をもう少しきちんと理解したいなと感じました。
今回はキリスト教徒の友達(エルサレムも案内してくれた)と一緒に巡り、こういう場所なんだよ~という解説までしてくれました。さもないと「ふ~ん」で済ませてしまいがちな、史跡や教会…。どれもこれも「意味のある場所」だとと認識して回ると、より楽しめます。
ペテロ、イエス、福音書…など全く分からない私のような駐在員でも、異世界っぽさのある景色や美しいガリラヤ湖を眺めているだけでも、大きな癒しを得られる場所です。
ガリラヤ湖周辺はレストランなど食事をとれるところがほぼないので(ガソリンスタンドのスーパーならあります)、飲み物や軽食を用意して訪れることをお勧めします。
そして6月上旬でも歩き回るととても暑かったので、帽子やサングラスなどの避暑アイテムも必須です。
今回の記事内では割愛しましたが、ティベリア地方には「偉大なラビ(ユダヤ教の宗教家)の墓」も数多くあり、ユダヤ教徒の礼拝経験もできます。シナゴーグ巡りも楽しいですよ。
信仰心の有無にかかわらず、イスラエルにいる「今」だからしか巡れない場所に行けることも、駐在生活のありがたい副産物です。