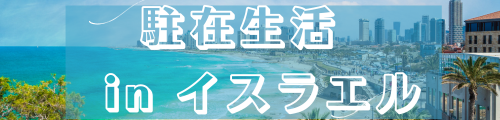【イスラエル駐在1年】2025年・春の祝日「ペサハ / Passover」到来。イスラエルで二度目の「過ぎ越しの祭り」体験!

シャバット・シャローム、a-box-of-chocolateです。もう日中はTシャツで過ごせるほど暖かくなってきたテルアビブ。4月と言ったらペ・サ・ハ、ペサハと言ったら春~、という連想ゲームができそうなほど、春を象徴する祝日、「ペサハ(Passover)」の季節がやってきました!
ちなみに、ヘブライ語で「アビブ/ אָבִיב」は春を意味します。空も海もきれいですし、街路樹や花壇も美しい、テルアビブは、まさに春満開です!
目次
【過ぎ越しの祭り】ペサハとは?何をどう過ぎ越したのか?イスラエル人が大切にする祝日について。
ペサハという祝日は、2025年4月12日(土)の夕方から始まり、19日(土)まで続きます。
まず、表現がバラバラなのでまとめます。
〇ヘブライ語→ペサハ(פסח)※「ハ」は喉音。
〇英語→Passover (パスオーバー)
〇日本語→過ぎ越し(昔ながらの直訳?なのか、少し違和感ある言い方です)
昨年4月もイスラエルにいましたが、引越の片付けや生活の立ち上げなどに追われて、祝日の意味など深く考えることもなく過ぎていきました。文字通り「過ぎ越したホリデー」だったわけですが…イスラエルの盛大な祝日「ペサハ」。一週間続くお祝いウィークです。
パスオーバー(ペサハ)の意味・由来
★ 歴史的背景
パスオーバーは、ユダヤ人がエジプトでの奴隷生活から解放された出来事(出エジプト記)を記念する祭りです。
旧約聖書『出エジプト記』によると、神はモーセ(預言者)を通してファラオ(エジプト王)に「イスラエルの民を解放せよ」と命じましたが、ファラオは拒否。すると神はエジプトに10の災いを下します。
その最後が「エジプト中の長子(長男長女)を神が撃つ」というものでした。しかし、ユダヤ人は神の命令に従い、家の門に子羊の血を塗ったおかげで災いが“過ぎ越された”(=Pass Over)ため、それが祭りの名前の由来になりました。
めでたし、めでたし。
https://www.history.com/articles/passover
…というのが概要です。
登場人物も、それぞれ誰?という知識しか持ち合わせていない私ですが…
ユダヤ教の神は、イスラエルの民たち(ユダヤ人)に「子羊の血が塗られた家には災いを下さない、通り過ぎる(Pass Over)」と約束し、そのとおりに行動した(神を信じて従った)者たちを救った、ということです。
そしてモーセが(当時奴隷だった)イスラエルの民を連れてエジプトを脱出、奴隷からも解放されて万歳!と続きます。
★ペサハの意味
- 「過ぎ越す」という意味のヘブライ語の動詞“פָּסַח(パサハ)’’に由来
- 神がユダヤ人の家を「過ぎ越した」ことを記念して、この祭りは「ペサハ(Passover)」と呼ぶ
★ 祭りの特徴
- 7日間または8日間続く
- この期間中は発酵したパンを食べない
- マッツァ(無発酵パン)を食べ、セーデルという特別な儀式的食事を行う
- セーデルでは、特定の料理を通して出エジプトの物語を子供たちにも教える教育的な意図もあり
豪華な会食を一家総出で楽しむ、伝統的な食事の儀式・「セーデル」
IWCのイベントで、ペサハのテーブルマナー講習会&伝統料理の試食会イベントがあったので参加しました。こちら、とある会員のご自宅で開催されたのですが…なんて豪華絢爛なマンション&テーブルデコレーション!!
長テーブル、家族全員が対面で座って食事する、というのがユダヤスタイルなので、8人から10人掛けの長~いダイニングテーブルを所有しているお家が多いです。日本の住宅事情では考えられません!!
そしてこの、くぼみがある銀色の食器(セーデル・プレート)にも意味があります。

☆セーデル・プレートに入れる6つのシンボル
| 名前 | ヘブライ語表記 | 意味 |
| ゼロア | זרוע | 焼いた骨付き肉(通常は羊の骨)→ 神の「伸ばした腕」(出エジプトの力)を象徴 |
| ベイツァー | ביצה | ゆで卵(時にロースト)→ 嘆きの象徴、または巡礼祭の供物 |
| マロール | מרור | 苦菜(ホースラディッシュやロメインレタス)→ エジプトでの苦しい労働を象徴 |
| ハロセト | חרוסת | 甘い果物のペースト(ナッツ・りんご・ワインなど)→ レンガ作りの泥を象徴。でも甘いのは希望を表す |
| カルパス | כרפס | セロリやパセリなどの青菜→ 春の訪れと新しい命。塩水につけて食べる(涙の象徴) |
| ハザレト | חזרת | 2種類目の苦菜(マロールと重複する場合あり)→ 苦味の再強調。レタスが多い |
食べ物を何かのシンボルに見立ててお祝いするのは、ユダヤ教の大きな特徴だと思います。
それぞれに意味をもたせるところは、日本のお節料理に似ているところがあるようにも感じました。
洗練された食器を集めている方も非常に多いです。さらにナプキンの折りたたみ方、お皿の積み重ね方など、こだわりと伝統に尽力する食事「セデール」。
メインディッシュは、魚の煮込み料理だそうです。イスラエル人はベジタリアンも多いし、野菜たっぷりのラインアップ。
春のお祝いなので、色鮮やかになることも大切なポイント!
アシュケナジーというロシア系ユダヤ人は、魚のすり身を団子にして、甘い餡をかけて食べるそうです(写真中央、にんじんが乗っているつくね)。おでんに入っているイワシのつくねみたいな味がしました。
この「マッツァ」というグルテンフリーパン?小麦を使わないクラッカーは、ペサハ期間の主食になるようです。
☆なぜ小麦が禁忌?発酵=“ハメツ(חמץ)”がNGな理由
ユダヤ教では、小麦・大麦・スペルト小麦・ライ麦・オート麦の5種類の穀物が、水と混ざって18分以上放置されると“発酵(ハメツ)”したとみなされます。
ペサハ期間中、このハメツ(発酵した穀物)は一切口にしてはいけない、というのが厳しいルールです。
これを聞くたびに、【破滅=ハメツ】、を連想してしまいます…。
背景には、出エジプトの物語があって、その一説には以下のシナリオがあります。
”イスラエルの民は、ファラオの命令で急いでエジプトを出発しなければならなかった。パンを発酵させる暇がなく、生地をそのまま持って旅立った。そのため、発酵していない「マッツァ(無発酵パン)」だけを食べて旅を続けた。”
この記憶を忘れないように、ハメツを完全に断つことがペサハの戒律になりました。
この期間、徹底的に小麦粉を含めて小麦製品を断捨離(文字通り全捨て!)したり、キッチンの大掃除をして小麦製品が残らないようにしたり、伝統を重んじる人は徹底的に小麦排除に尽力するそうです…。
そして、物理的にもコーシェルを守っているお店では、小麦製品が買えなくなります。
マッツァ(複数形:マツォット)とは、こんな巨大な箱買いする食べ物なのです…。一週間分の主食ですから!可もなく不可もない味。
10日の夕方にスーパーに行ったら、小麦製品は既に売っていないことになっていました。さすがにお店で売っているものは捨てていませんが、「隠して販売しない」手段がとられます。
一週間のフェスティバル。無料開放される博物館や美術館も♪家族でのんびり楽しむ=ペサハの醍醐味!
イスラエル人にとって、ペサハは「家族団らん」の大切な時間。親戚一同が集まって、食事を楽しみ、伝統を後世に伝える大切なイベントなのです。
子どもたちは春休み期間なのもあり、イスラエル中の博物館、美術館、国立公園などが無料開放されています!
全てではないのですが、Bank Hapoalimという大手銀行がスポンサーとなり、全国60か所を無料で訪れることができます。なお、無料利用するには事前登録が必要です。
レバノンとの国境付近や、ガザとの境界付近など、戦争のせいで閉鎖を余儀なくされたエリアも、このパスオーバー期間だけ特別に無料開放されています。(安全に遊べるのかどうかはまた別として…)
戦争によって過疎化してしまった地域に人を呼び戻して、「いつもどおり」に近づけることが目的だと述べられています。そのためのスポンサーシップ、なかなか粋な計らいです。
私も、来週はイスラエル各地の様々な博物館や公園の入場券を予約しました!その様子は、また次回の記事でお届けしたいと思います。