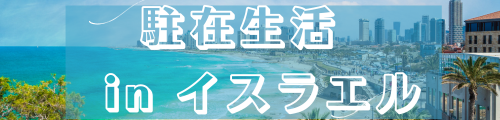【イスラエル駐在1年半】心が折れ始めた、独学でのヘブライ語学習。駐妻の現地語習得は本当に必要?

お久しぶりです、a-box-of-chocolateです!全く秋の気配を感じられないほど暑い、11月のテルアビブ。まだまだTシャツで快適ですし、午後からは暑くてエアコンつける日もあります。雨も降らないし、空気も乾いていて、街全体のほこりっぽさが増しているような気がします…。
気づけばイスラエルでの駐在生活は一年半を超えました。戦争は終わりそうで終わらない、そんな宙ぶらりんの状況が続いています。イスラエルとはどんな国なのか、ユダヤ教徒はどんなものなのか、少しずつ分かったような、まだまだ理解できないような。とても不思議な国です。
「自分が暮らしている国がどんなところなのか?」を知りたいという好奇心で始めた、ヘブライ語学習。単刀直入に言うと、【駐妻がちょっと努力したくらいでは全く習得できない言語】だという諦めの境地に達しているのです…。今日はそんな、「現地語の習得」について綴っていきます。

目次
ヘブライ語学習これまでの記録
ヘブライ語学習、モチベーションが急激低下。どうしたら現地語学習を「習慣化」できる?
今年の5月末まで、駐在員向けのヘブライ語オンライン学習グループ(ボランティアレッスン)に週に一回(1時間)ほど参加し、終わったらその日に習ったことを復習する、というルーティーンを重ねていました。
さらに、以前の記事でも紹介した「Hebrew Pod 101」というサブスクリプションサービスに加入して、文法&語彙力向上のための自主学習も、ちょこちょこと隙間時間に行っていました。ヘブライ語の自主学習ノートも4冊目に突入し、なかなかいいペースで頑張っていました。そして、デュオリンゴも必ず一日一回はログインして、1レッスンは必ずやる!というルーティーンも定着していました。
はい、お気づきのとおり、「すべて過去形」なのです。

私の過去の栄光、Duolingoのストリーク(連続学習日数)178日。これは7月中旬の話です。
その言語知識、本当に必要ですか?という悪魔の囁き。
ここまで積み上げていたものが一気に崩れた原因は、「日本への一時帰国」でした。デュオリンゴだって、HebrewPodだって、スマホのアプリなのでやろうと思えば世界中のどこでもできるのです。
しかし。イラン戦争後のイスラエルから脱出できる!!!!という喜びに満ち溢れていた私は、今年の夏休みは「イスラエルに関わるものを全てシャットアウトする」というデトックスタイムを敢行。
日本のテレビで見るテルアビブのニュースは、どこか見知らぬ遠い国の出来事に思えましたし、サイレンや警報、シェルターに駆け込んで怯えていた日を彷彿とさせる情報、食べ物、言語、すべてシャットアウトしました。
そう、つまりヘブライ語にも一切触れませんでした。普通に日本で暮らしていて、ヘブライ語が聞こえてくることなんてありませんし、そもそも誰かが喋っていたとしても、それをヘブライ語だと認知できる人も、ほとんどいないと思います。
こうして日本で過ごした3週間あまりで、私はヘブライ語のことを(意図的に)考えることをやめたので、もちろんデュオリンゴも一度も使いませんでしたし、ヘブライ語を耳にすることも声に出すことも全くないまま、「楽しい日本での夏休み」に没頭したのです。
そうこうしているうちに、ふつふつと湧き上がってきた疑念が、【本当にヘブライ語を学ぶ必要性があるのか?】ということ。必要、不要、の二択で選ぶのであれば、断然後者であり、【不要】です。
こんなに頑張って覚える必要ある?っていうか、勉強してみてはいるけど、使えるレベルに達するには、あと何年かかる?
そんな悪魔の囁きにも近い「ヘブライ語やらなくてもよくない?」という気持ちに一度でも引っ張られると、人間、楽な方へ流されるのは簡単なのです…。
極論、英語が分かれば生活での苦労が無いイスラエル。
日本で3週間過ごしている間は、英語すら話す必要がなく、「日本語だけできれば幸せに暮らせる日本って最高じゃん!!!」と何度も思いました。
母国語で全て完結できる国にいて、他の国の言葉を学んで「生活の中で使う必要性」がなければ、その言語を学ぶモチベーションが低くなる。日本は、そういう意味では本当に恵まれています。一つの言語ですべての生活、仕事、教育、なんでも完結できるのです。
それと全く同じ原理で、英語でほぼ全て完結できる国に暮らしていて、たとえ現地語(その国の母国語)だとしても、「生活の中で使えるレベルに達していない言語」は学ぶモチベーションが低くなる。
まさにそんな「沼」にハマってしまったのです。
イスラエルに来てから出会った人で、「ヘブライ語だけしかできない」という人は果たしているのだろうか?と感じています。多言語環境でで育ってきたり、仕事のために語学を身につけたという人が大多数です。
イスラエルに駐在している人たち(インターナショナルクラブで出会った友人たち)もまた然り、英語しか話せないという人は稀で(一部のアメリカ人くらい?)、2~3か国語堪能である人たちのほうがマジョリティです。
そもそもイスラエルという国家は1948年に建国されていますが、当時の人口は約100万人。そして現在は1000万人です。イスラエルで生まれた人たちだけでなく、アリヤ―を行い「イスラエル国民になるために移住してきた人たち」も大勢います。(そのためにウルパンが存在し、移民たちはヘブライ語を習得します。)
ヘブライ語ネイティブスピーカーとしてイスラエルで生まれ育った人はどのくらいいるのか、非常に興味深い点でもあります。
このように、元々は別の言語を話していて、+アルファでヘブライ語を身につけた移民もいれば、イスラエルで生まれ育ち、徴兵や仕事のために英語を身につけた国民もいます。そして移民二世は親世代の元々の言語(英語、ロシア語、フランス語など)&現地学校でヘブライ語を身につけるパターンもあるので、「家族全員単一言語しかできない(=日本)」みたいな現象は、なかなか起きないのでは??というのが、私が感じるイスラエルです。
もはや、ただの言い訳でしかないのですが…「家族全員日本語しか喋っていない」ところで生活している私にとって、ヘブライ語が劇的に伸びていく要素はゼロ。ヘブライ語を使って仕事をしたり、学校に通ったりするわけでもないので、その必要性はますます薄れていきます。
【悲報】私のショボすぎるヘブライ語が通じず、英語お助けマン参上!
体感、7割近い人が英語で会話できるテルアビブに住んでいると、私の知識を総動員してヘブライ語をしゃべってみても、発音が悪すぎて通じていない。まだこのレベルなのです…。
ただ、本当に英語が全く話せない人にも(肉屋とか魚屋とかで)遭遇することもあるので、そのときは単語レベルの知識でコミュニケーションを試みます。
たとえば、「鳥の皮いる?」= tzarif or? みたいなことを聞かれて、 or(オル)ってなんだっけ?指さしてる様子からして「皮(skin)」のことだよな?と推測できる程度には、役に立ちます。
ただ、or/ עוֹרの発音が通じてる可能性は低いです。
ひき肉=בָּשָׂר טָחוּן, basar tachon も、一瞬怪訝な顔されますが、grind, that machine, グルグル回すジェスチャーなどを総動員すれば、どうにか相手もわかってくれます。
ヘブライ語は「最低限のサバイバル言語」としか使えないレベルから脱却できないのですが、「言語=コミュニケーションツール」という視点で見れば、十分だとも言えます。その辺の犬の方が、よっぽど飼い主が話すヘブライをわかっていることでしょう。
そして何より!私は外見(アジア人)からして「ユダヤ人」の可能性が限りなく低い、と周りが先に判断してくれるので、ヘブライ語よりも先に英語で話しかけられることのほうが圧倒的に多いですね。
さらに!どんな場所に行っても、必ず一人以上は「英語が話せる客」がいるため、私と店員さんがトンチンカンなやり取りをしていると、「〇〇って言ってるよ」と教えてくれる、親切な通行人がいるのです~!!
もっと言えば、こっちがヘブライ語わかってなくてもお構いなしな人もいて、私もそれはそれでいいかな~と思っているので、適当にken, ken~~と相槌を打ってみたりします。(笑)
日常生活で、言葉と行動を結びつけてヘブライ語を覚える!
結局のところ、机の上での独学に限界を感じてきている、というのが本音です。アプリ学習を通して単語を読んだり書いたり、なんとなく勉強した気になってみても、何も定着していないので全く日常生活で使えないのです…。
以前も言いましたが、イスラエルに住んでいるからと言って、ヘブライ語をペラペラと自動的に喋れるようになる…などという魔法のような出来事は全く起きていません。
ただ、人々がしゃべっている言葉を聞いていると、イントネーションだったり発音の仕方だったり、よく聞く単語だったり、というのは段々とわかってくるものです。
やはり言語学習の本質とでも言うべきですが、実践的な場面で、自分の体験・経験と言葉を結び付けて覚える、という最も原始的な方法をとる以外、言語スキルが伸びていく(自分の言葉として蓄積されていく)実感を得るのは難しいだろうな、と感じています。
たとえば買い物中だったり、ボランティアグループで果物や野菜の収穫ボランティアをやっているときだったり、自分が実際に手に取ったもの、そのとき話していた人、場所や場面、そういう五感と言語が連動すると、きちんと定着するのです。

一気に語彙を増やすことはできませんが、たとえば野菜の名前だったり色だったり、一日に数単語、数フレーズ知るだけでも、私は満足です。
使う必要がない言葉を無理やり覚えるのが、いかに大変なことなのか!身に持って体験しています。
結論:現地語がペラペラになる必要なんてない!ただ、その国の人々と文化について知ることは大切。
そもそも、なぜ私はヘブライ語を学んでみたいのか?という原点回帰してみると、それはヘブライ語がペラペラになって現地の人と会話したいとか、イスラエルで仕事したいとか、日常に密接した理由ではなく、「その国のこと、文化について、言語を通して知りたいから」なのです。
それなのにウルパンに通ってみる、といった無茶をした昨年春でしたが、今となって思うのは、ウルパンのℵクラスは神。ウルパンはインテンシブコースに一か月通っただけですが、その一ヶ月で習ったことが、すべてのその後の学習の基礎を支えています。
さて、ヘブライ語という未知の言語と格闘した1年半で、私が「イスラエル」についてわかったこと・感じたこと(素人感想)を述べてみます。
●とにかく効率重視。短く、わかりやすく話すことが正義。
●敬語表現はないので、言い方が直接的。回りくどいのはみんな嫌い。
●単語で会話しても、失礼じゃない。
(例)
日本「いらっしゃいませ。当店の会員カードはお持ちでしょうか?」
イスラエル「モアドン?(membership?)」(一単語)
●声がでかい。そんなに大声じゃなくても聞こえるよ?というほどの圧を感じる。
●英語がペラペラ話せる人が多いけど、「ヘブライ語訛り」というかヘブライ語に引っ張られたイントネーションで話している人もけっこういる。(日本語訛りだって恥じることない!)
●「ディスカッション」の域を超えて、怒鳴り合うほどテンションマックスで話している人が多い。血気盛ん。
ヘブライ語の語彙バリエーションが日本語ほど多くなく、シンプルな言語構造のためか、(それでも私には難しい!)「大声、直接的表現、畳み掛けるようにしゃべり続ける」という話し方の加減次第で自己主張をしているのかな?と思うことが多々あります。
「すみません、少しお話してもよろしいですか。」「少々お話させていただくことは可能でしょうか。」「ちょっと話していい?」という日本語表現があったとして、それに相当する「~してもいいか(possible to do)?」というヘブライ語は(efshar) אפשר で済ませられます。そう思うと、日本語の方が圧倒的に難しいですね。
他人を慮って、知らない人であればあるほど単語を増やしてしゃべる=距離をつくる日本語の文化とは対極で、シンプルに、ストレートに、自分の気持ちを明確にわかるようにしゃべることが良し、とされているイスラエル文化。ごにょごにょっと小声で喋る日本人なんて、一番イライラさせられるのでは?とびくびくします。(笑)
それはvice versa, 道端でイスラエル人にぶっきらぼうに話しかけられて、「え、私なんかした?この人怒ってる?」と思うこともあります。特にスーパーやカフェの店員が、潔いほどにやる気ない(なげやり)のは、「この仕事やりたくない、というのをストレートに表現しているのかな?」と感心してしまうほど。(たぶん違います、ただのサービス低下!)
反対に、飛び切りの笑顔で通行人から「ma nishma-?」(How are you?)と声かけられることもあるので、言葉と気持ちが表裏一体なんだな、というイスラエル文化&ヘブライ語のコンビネーションは、けっこう気持ちがいいです。
そう思うと、日本語のコミュニケーションはまどろっこしいですね。。。
さて、ヘブライ語の独学に心折れてモチベーション低下が続いている私ですが、「言語知識として学ぶヘブライ語学習」に飽きてきているのであって、「ヘブライ語をしゃべっているイスラエル人」への興味は増す一方です。何言ってるか分からない場面が大半ですが、ずーっとヘブライ語を聞いていると、なんだか分かる気がしてくるから不思議です。(笑)
駐在生活で、現地語を獲得しないと生活できないところにお住いの方もいるかと思います。最近イスラエルからドイツに異動になった友人は、英語があまり通じない地域に住んでいるせいか、やはりドイツ語の語学学校に通わないとだめかも!と漏らしていたので、住む場所によっては、その国の言葉を学んで、生活言語を身につける必要性があるかと思います。
ですが、その点ではイスラエルは大丈夫です!ヘブライ語に全情熱をかけるのであれば、英語をやったほうがいいかな?と思うほど。多言語環境が当たり前の国で、リンガフランカ(英語)がこんなにありがたいと思ったのも、初めての体験です!

声を大にして言いたい。日本語ネイティブに生まれてきたこと、日本人として海外で駐在生活できることは、人生最大の大当たりガチャなのです!!ヤパン・ヨッフィー!